「自費診療に変えようと思うけど何から始めたら良いのか…」
「もう不正には手を染めたくない、保険診療を辞めるには何から始めたら良いのだろう」
こんなお悩みを解消する方法をブログにまとめさせて頂きました。
リスクを避けて保険診療から自費診療に変えるためのステップ
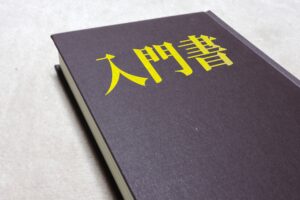
こんにちは、治療院成功塾を主催しています作尾大介と申します。
この度は、保険診療から自費移行するときに極力リスクを避けて、実行する方法をまとめさせて頂きました。
「行政の締め付けで診療単価が下がった…このままでは食べていけない」
「これからは、保険診療がメインでは整骨院の経営が難しい」
と、お考えでしたらこの度の記事がきっとお役に立てると考えています。
もし、自費移行をお考えでしたら、この度の記事と合わせてこちらの記事がお役に立てるかもしれません。
自費移行すると保険診療で来院されていた既存の患者さんが来院する方法

失敗しない、自費移行の手順をおさらいすると
1.各種保険取扱等、保険を連想させるステッカー・ポスター等を剥がす
2.家族やスタッフに自費移行をする旨を伝えるてコミットメントを取る
3.院内掲示物で○月○○日までに保険診療をやめるという旨をアナウンス
ということを順番に取り組んで頂いたのちに、この度のブログの内容を実践すると失敗のリスクを避けることが可能になると考えています。
自費移行のために取り組んで頂くことは、
今まで来院された患者さんに向けて保険診療から自費移行する旨をお知らせするお手紙を書くことです。

「いや、これは口頭で伝えたし、院内掲示板にも貼ってるから大丈夫」
私は最初そのように思っていました。
ですが、この方法は日ごろ来院なさる患者さんには有効ですが、今まで整骨院に来院されていた患者さんには
・施術料金が変わる
・整骨院のシステムが変わる
・施術に特化した整骨院になる
・保険診療を辞めて自費移行する理由
と言ったことを周知して頂くことができません。
「保険診療でも来院されなかった患者さんが、施術料金もあがったのに来院するのか?」
そんな不安があるのも、無理のないことかと思います。
ですが、私の自費移行の経験と今まで自費移行のサポートをさせて頂いた先生の事例を見ると、
保険診療をやめる手紙をみて来院なさる患者さんもいらっしゃるのです。
中には、
「こんな整骨院を探していました」
「まじめな先生だからこそお願いしたい」
と、有難い言葉までいただけることもありました。
自費移行の思いの丈を込めた手紙こそ、家族やスタッフの力を借りましょう

グレーな保険診療は一切やめ、自費診療の整骨院にする。
初めて施術家を志したころの気持ちになって0からスタートする!
こんな思いを込めて手紙を書くと、たいていの場合、熱い思いが入って何を言っているのか分からない文章になる傾向があります。
ですので、このお手紙に関しては誰かに添削を受けることをオススメします。
一般の方が分かりやすい言葉や表現を使ってお伝えすることで、来院なさる患者さんも増える可能性があります。
療養費や受領委任と言われても、業界の方以外はいまいち理解ができません。
こんな問題を解消するためにも、家族や、仲の良い友人の方に手紙の内容を添削して頂くことをオススメしています。
整骨院を自費移行するお知らせは手紙が良い?それともハガキ?

自費移行をお知らせするツールはハガキがいいのか?
それともお手紙がいいのか?
と言った相談をとよくお伺いします。
もし、予算に余裕があるときは両方とも送ることをオススメしています。
手紙で出したのであれば、3週間後にもう一度ハガキで出す。
ハガキで出したのであれば、1ヶ月後もう一度お手紙を出す。
手紙を出しても開封されないこともあります。
でも、ハガキを送ることで周知していただける可能性が高まります。
この戦略で、2か月くらいの時間をかけて整骨院のシステムを変えていければよいと思われます。
音声 https://anchor.fm/9870/episodes/ep-e17168j
今までご縁をいただきました患者さんに向けて、手紙やハガキで自費移行をする旨を周知する。
これが自費移行の4つ目のステップとなります。
最後に
もし自費移行をお考えでしたら、治療院成功塾のコンテンツがお役に立てると考えています。
治療院成功塾では
・保険に頼らずに整骨院を開業する
・保険診療をやめて自費診療で安定した整骨院を経営する
ために必要なコンテンツを学んでいます。

もし治療院成功塾に興味がりましたら
「このブログに書いてる事って本当かな」
「一体どんなことを学んでるんだろう」
ぐらいの気持ちで下記QRコードかURLを読み込んでいただき、LINEの方からお気軽にメッセージをいただければすぐに返信させて頂きます。

整骨院の自費移行や開業でお悩みでしたらお気軽にご相談いただければ幸いです。
(監修 柔道整復師・鍼灸師 作尾大介)
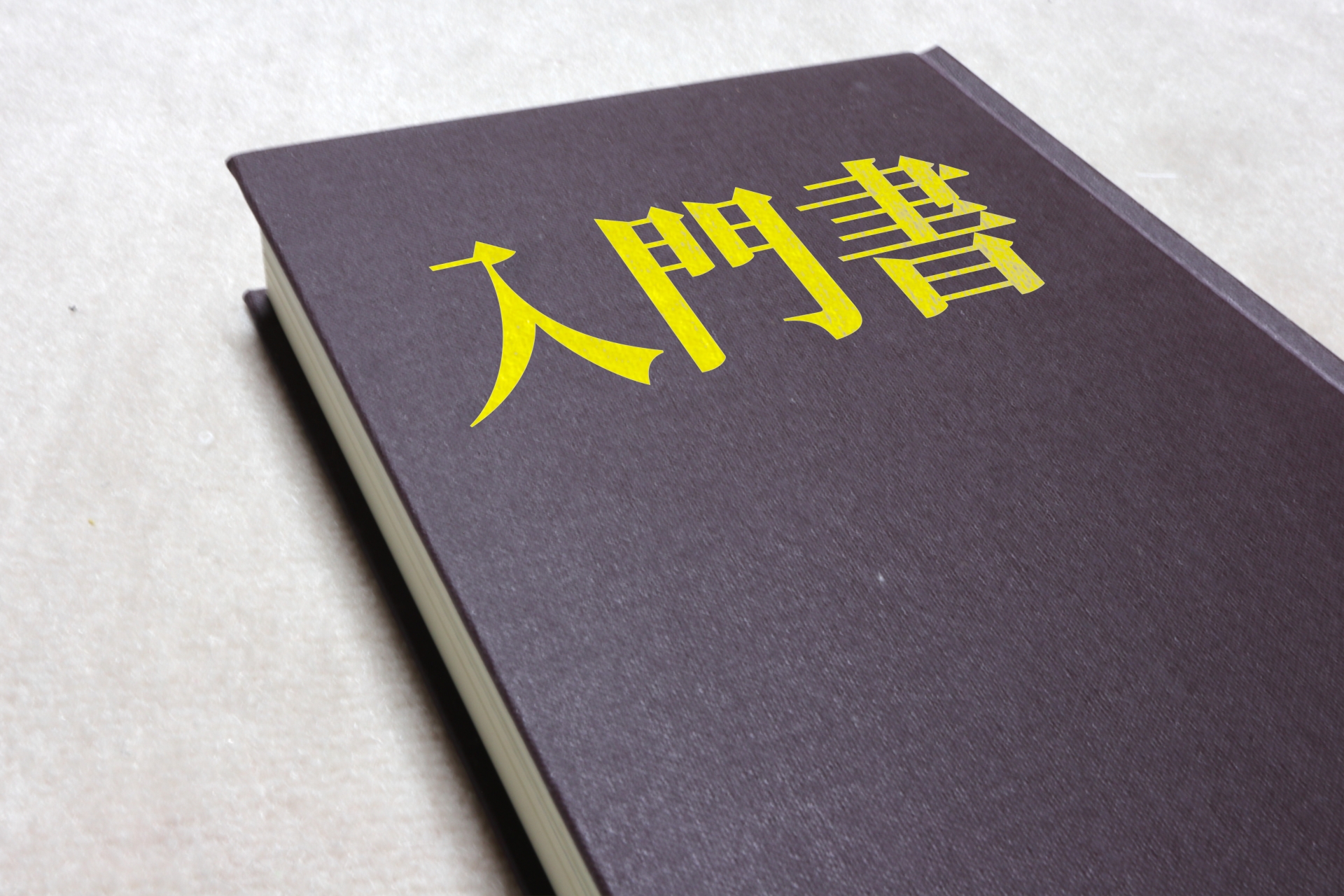







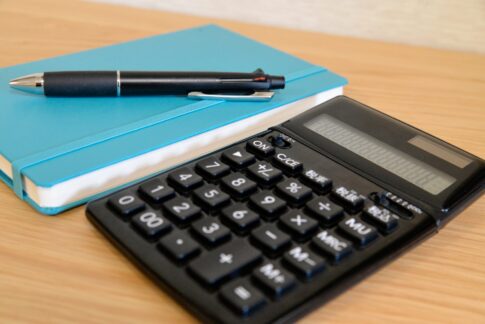

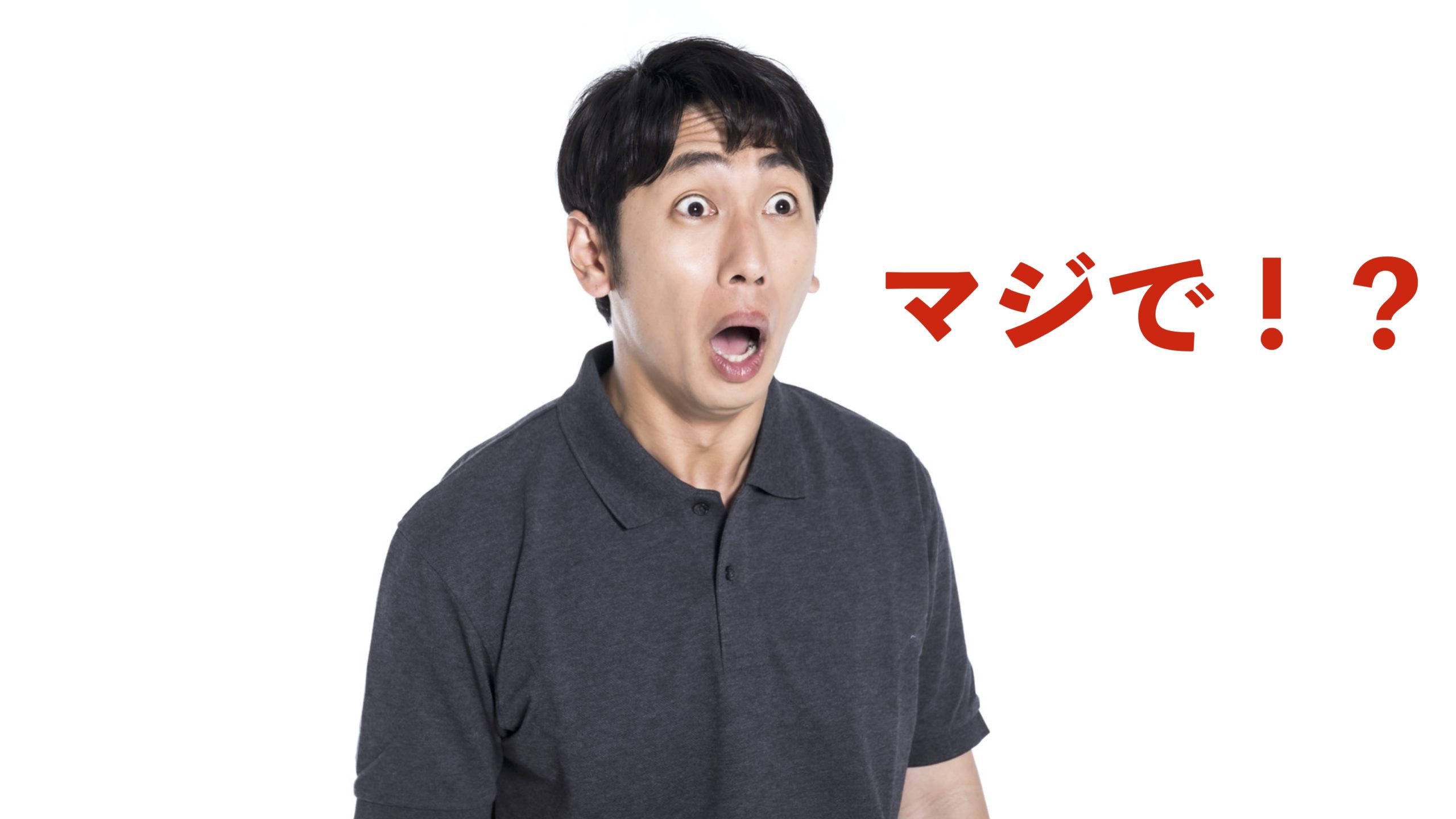
コメントを残す